前回に続き、ニュートン著「プリンシピア」の第1巻に記されたニュートンの絶対時空に対する考えをご紹介し、今日的な観点からこれに批判を加えてまいります。時間につきましては前回ご紹介しましたので、今回は空間について議論いたします。
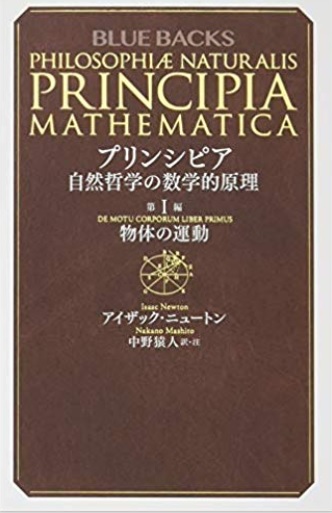
ニュートンのプリンシピアでの空間の扱い
ニュートンの空間概念は、ニュートン著「プリンシピア」の第1巻の中で、前回ご紹介しました時間概念に続く箇所(P31)で、以下のように述べられています。
II. 絶対的な空間は、その本性において、いかなる外的事物にも無関係に、常に同形、不動のものとして存続する。
相対的な空間は、絶対的な空間のある可動な寸法あるいは測度であって、諸物体に対するその位置により、われわれの感覚がそれを決定するが、普通にはそれは不動の空間と考えられる。地球に関するその位置によって決定される地下、空中、あるいは天空の空間の広がりのようなものが、すなわちこれである。
絶対空間と相対空間とは、形と大きさを等しくするが、しかし、それらは常に数値的に同一ではない。なぜならば、もしたとえば地球が動くならば、地球に関して相対的に、しかも常に同一の状態にあるわれわれの大気という空間は、あるときはその大気が通過する絶対空間の一部であり、あるときは同じものの他の一部であり、したがってそれは絶えず変化すべきことが絶対的に理解されるからである。
原著(ラテン語版)では以下の通りです。
II. Spatium absolutum natura sua absq; relatione ad externum quodvis semper manet similare & immobile; relativum est spatii hujus mensura seu dimensio qualibet mobilis, qua a sensibus nostris per situm suum ad corpora definitur, & a vulgo pro spatio immobili usurpatur: uti dimensio spatii subterranei, aerei vel calestis definita per situm suum ad Terram. Idem sunt spatium absolutum & relativum, specie & magnitudine, sed non permanent idem semper numero. Nam si Terra, verbi gratia, movetur, spatium Aeris nostri quod relative & respectu Terra semper manet idem, nunc erit una pars spatii absoluti in quam Aer transit, nunc alia pars ejus, & sic absolute mutabitur perpetuo.
Andrew Motte氏訳の英語版では以下の通りです。
II. Absolute space, in its own nature, without regard to anything external, remains always similar and immovable. Relative space is some movable dimension or measure of the absolute spaces ; which our senses determine by its position to bodies ; and which is vulgarly taken for immovable space ; such is the dimension of a subterraneous, an aereal, or celestial space, determined by its position in respect of the earth. Absolute and relative space, are the same in figure and magnitude ; but they do not re main always numerically the same. For if the earth, for instance, moves, a space of our air, which relatively and in respect of the earth remains al ways the same, will at one time be one part of the absolute space into which the air passes ; at another time it will be another part of the same, and so. absolutely understood, it will be perpetually mutable.
ここでニュートンが主張しているのは、不動の絶対的な空間が存在するということ、われわれが感覚的に把握しているのは、絶対空間の一部だが絶対空間に対して移動することができる空間で、たとえば地球上のある領域を切り出したものがこれにあたります。
われわれはこの相対空間を不動のものと考えているのですが、地球が動いているなら、この相対空間は、絶対空間の一部だが、時間の経過に伴い絶対空間の異なる一部に相当しています。
このニュートンの相対的な空間概念は、地球が移動している以上当然の話なのですが、その前にあります、不動の絶対空間が次に批判を浴びることとなります。
否定された絶対空間
ニュートンの不動の絶対空間に関しては、その後批判が相次ぎ、今日ではこの考え方は否定されております。
以前のこのブログでご紹介した、マックス・ボルンによれば、結論は以下のようになります。
こうして古典力学の相対性原理は、つぎのような形になる。
互いに相対的に並進運動を行っている無限に多くの等しく正当な系―慣性系―が存在し、これらの系では力学の法則はその単純な古典的な形式のままで成立する。
英語版では以下の通りです。
The principle of relativity then assumes the following form :
There are an infinite number of equally justifiable systems, inertial systems, executing a motion of translation with respect to each other, in which the laws of mechanics hold in their simple classical form.
つまり、不動の絶対空間は存在せず、無限に多くの等しく正当な慣性系が存在する、というわけです。
絶対空間はなぜ必要とされたか
私はニュートンが絶対空間を前提とした理由がなんとなくわかります。
実は、ニュートンのプリンシピアが出版され天動説・地動説問題に最終解が与えられたのが1687年なのですが、ガリレオが「天文対話」を出版したのが1630年、これを受けた1633年の裁判で有罪とされ「有罪が告げられたガリレオは、地球が動くという説を放棄する旨が書かれた異端誓絶文を読み上げた(Wikipedia)」わけですから、この間わずか50年あまり、天動説から地動説に移行し始めてから、さほどの時は経過していないのですね。
天動説か、地動説かという論争は、つまるところどちらが動いているか、という議論であり、地球が静止しているのか、太陽が静止しているのかが議論の中心であったわけです。ここに、「運動は相対的です」などという考え方は元々なく、絶対空間の存在が大前提となっていたのですね。
ただし、回転運動に関しては絶対的な静止空間があり得ます。つまり、回転していれば遠心力が発生するわけで、遠心力ゼロの空間は、少なくとも回転に関しては、静止しているといえます。
ニュートンは回転するバケツの例を示して絶対空間を正当化しているのですが、これが成り立つのは、回転運動に関してであり、等速直線運動する空間、つまり慣性系に対しては、無数の正当な空間(慣性系)が存在し得ることになります。
加速度を受ける空間の扱い
上に示したマックス・ボルンの言葉は古典力学の相対性原理であり、この範囲では慣性系相互の区別はつかず「不動の」絶対空間が否定されます。これは特殊相対性理論の結論とも同じです。
一方、一般相対性理論は、この考え方を加速度の作用する空間(加速運動する座標系)にも拡大し、加速度の作用する空間もまた静止しているものとして扱うことを可能としています。
エンジンをふかして加速するロケットの内部や、回転する円盤上にとられた空間は、空間自体が加速運動をするため、内部の物体にその質量に比例する慣性力が作用します。
この力は、外部の慣性系から観測すれば慣性力として認識されるのですが、加速運動している空間内部では、空間の歪によって質量に比例する力が発生したと説明されます。これが一般相対性理論で、加速運動する空間内部の物理現象は、その空間の内部にとられた座標系でも、座標自体の運動を考えずに、一応の説明はできております。
もちろん、その空間の歪が何によって発生しているかという原因を探れば、それは外部から重力が作用しているからであるとか、空間自体が加速運動をしているからであるといった説明が必要になるわけで、併進運動の場合と異なり、空間の動きを検出できないわけではありません。
地動説と今日の標準理論
17世紀に生じた天動説と地動説の対立は、人類の世界観を大きく変えた、エポックメイキングな出来事だったし、ニュートンも大きな発見をいたしました。
しかし今日では、すでにニュートンの理論は否定されている。少なくとも絶対時間と絶対空間は否定されており、何が動いていて何が止まっているかは、たいして重要な問題ではなくなってしまいました。
ニュートンの理論にとどめを刺したのは、絶対空間を探る試みであったといってもいいでしょう。かつては、電磁場を媒介するエーテルが存在すると考えられており、エーテルは絶対空間に固定され、静止していると考えれられておりました。だから、地球の対エーテル運動を計測すれば、絶対空間に対する太陽系の運動も知ることができると考えられたのですね。
しかしながら、精密な光速計測の結果、地球の対エーテル運動はないことが判明いたしました。これは、地球の絶対速度がゼロであること、天動説が正しいことを支持する結果でもあるのですが、さすがにこの時代になれば地動説が否定されるとは考えられませんでした。
この問題に最終的な解を与えたのが特殊相対性理論であったわけですね。この時点で、エーテルの存在が否定されるとともに、絶対空間も完全に否定されております。
観測者に固定された座標系
今日の多くの測定は地上で行われており、観測者に固定された座標系で様々な物理現象が計測されています。これは実は、天動説ベースの表現を採用している形となっているのですね。
厳密なことを言えば、地球は自転しており、太陽の周りを公転しており、太陽は銀河系宇宙の中で大きな回転運動をしており、銀河系宇宙は他の宇宙から遠ざかっております。
しかしこうした運動を物理現象の計測の中には一切取り入れることなく、観測者に固定された座標系で計測を行う。これはある意味では一貫性に欠ける行為であるともいえます。
しかしながら、計測結果を単純な形で表現するためには、地上に固定された座標系を用いるのが簡便です。そして、太陽系の惑星の運動を記述するには地動説が簡便であることから、結局のところ、何が動いているかという真実の追求ではなく、物理現象の単純な説明という、便宜的な目的のために視点を選んでいるのが実情です。
実際問題として、われわれが通常物理現象を記述する際に用いる時間軸は、地表の観測者に固定された座標系における時間軸であって、この時間軸に空間的な速度成分を含まないことは、観測者が静止しているとみなしていることにほかなりません。
つまり、一般的な物理現象の記述に際してわれわれが採用しているのは、地球表面上の観測者は静止しているとする、天動説に従う座標系を用いた記述がなされているのですね。
もちろん我々は同時に、ここで使っている時間軸(地表に固定された局所時間)は、無数にとりえる時間軸の一つにすぎず、他の時間軸を選んでも物理現象の記述は全く同様になされることを知っております。
多くの場合に、観測者に固定された座標系が選ばれるのは、それが計測を行う上で最も簡便な座標系だからであるにすぎないのですね。それ故、太陽と地球のどちらが動いているのかといった問題の立て方は、それ自体が無意味な問いの立て方であったわけです。
先験的自我と空間
観測者に固定された座標系は、先日のブログ(こちらがメインか?)で議論いたしました先験的自我の認識を本質とするカント流の世界観にも、最も適合いたします。
自我をすべての基本に置くのであれば、観測者を中心に世界を構成しなくてはいけません。このためには、観測者に固定された座標系で世界を記述する必要があり、観測者の運動の定数部分は慣性系として無視し、変動部分(加速度)は、空間の歪(それが故に慣性力や重力が生じる)として観測され、空間の歪を生み出す原因として空間自体の加速運動(回転運動も含む)が想定される、という形をとるのが、正しい認識ということになります。
天動説に地動説が取って代わるガリレオからニュートンに至る業績は、歴史的な意味合いはともかく、これらを今日の真実とすることには少々問題があり、より正しくは、カント流の哲学や相対論的見方をベースとするべきであるように、私には思われる次第です。
確かにニュートン力学や地動説はわかりやすい。でもこれは江戸時代の標準理論なのですね。人類の知性はニュートンの時代からずいぶんと進歩している。これが現実の姿だということを、もっと多くの人にわかっていただきたいと思います。